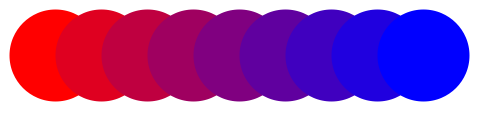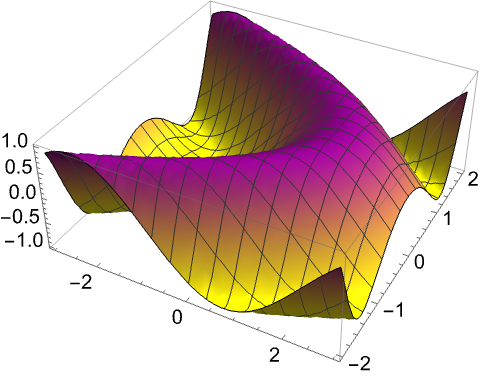Blend
✖
Blend
詳細

- Blendは,色付きの光源あるいは発色表示に適する加法混色を実装する.
- Blend[{col1,…,coln},{u1,…,un}]では,ui は合計が1になるように正規化される. »
- Blend[{col1,col2,…}]は,すべての coliを同じ割合で合成する.
- Blend[{image1,image2},x]では,image1 と image2 の次元が異なる場合は,次元の線形補間が使われる.
- Blend[{image,col},x]は,image のすべての画素を色 col と合成する.
- Blend[{image1,col1,…,coln,image2},x]では,coli は,次元が image1の次元と image2の次元の線形補間による画像であると解釈される.
例題
すべて開くすべて閉じる例 (4)基本的な使用例
スコープ (12)標準的な使用例のスコープの概要
色 (6)
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dkyals
Out[1]=1
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-kece9y
Out[1]=1
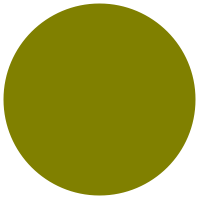
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-elrede
Out[1]=1

In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-iphmxe
Out[1]=1
In[2]:=2
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-5enwq
Out[2]=2

In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-db4mid
Out[1]=1
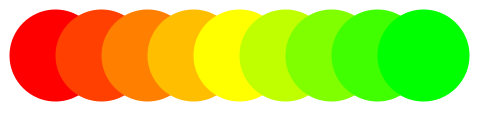
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-pksm6
Out[1]=1
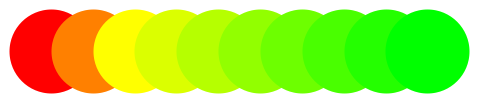
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gazpd6
Out[1]=1
In[2]:=2
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-czls70
Out[2]=2
In[3]:=3
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-c5is
Out[3]=3
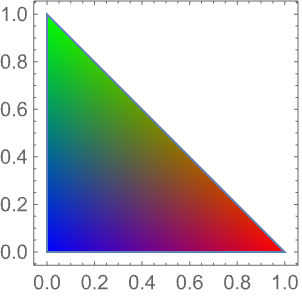
画像 (6)
In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-ynaac9
Out[1]=1

In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-zn7b7j
Out[1]=1

In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-c6hwtr
Out[1]=1

In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-iby1hl
Out[1]=1

In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-7fc6n0
Out[1]=1
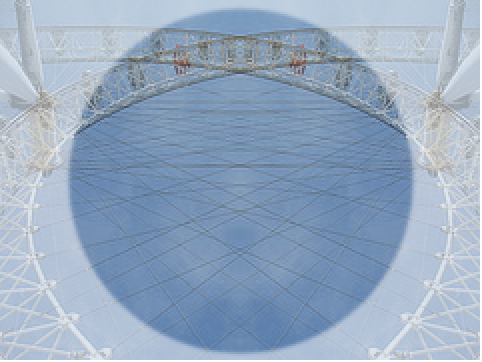
In[1]:=1
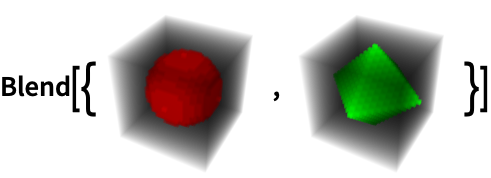
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gl7kkr
Out[1]=1
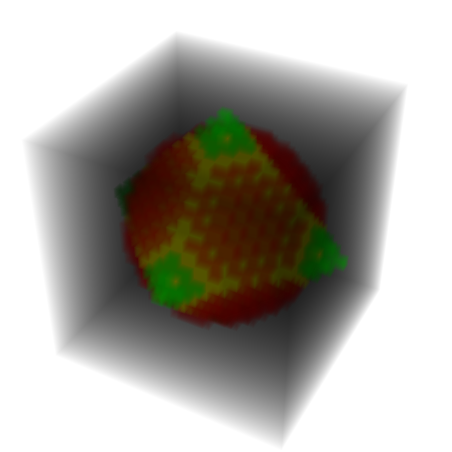
アプリケーション (2)この関数で解くことのできる問題の例
Blendを使って基調色からColorFunctionを構成する:
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-cxs32d
Out[1]=1
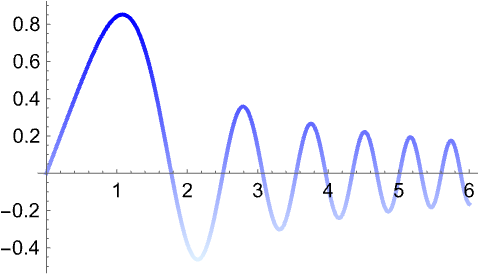
In[4]:=4
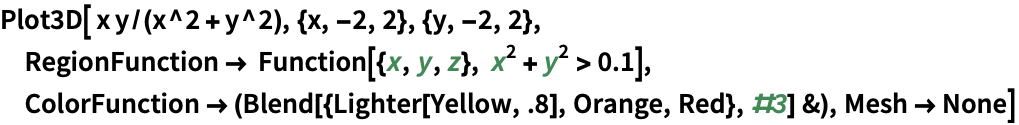
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-kvo42t
Out[4]=4
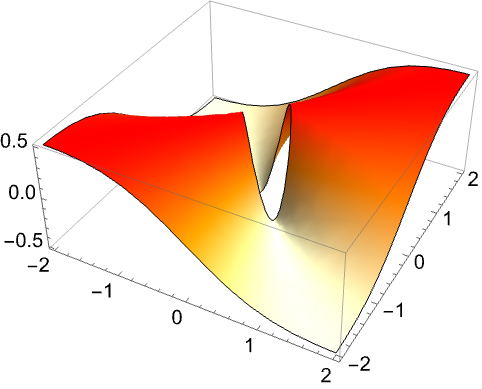
In[5]:=5
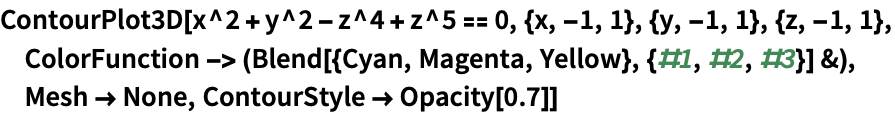
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-25dg0
Out[5]=5
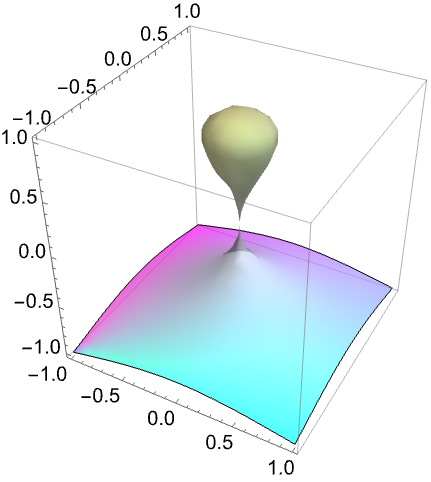
In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-scawmv
Out[1]=1

特性と関係 (7)この関数の特性および他の関数との関係
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-kwoiax
Out[1]=1
In[2]:=2
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-30lix2
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-h92d9b
Out[1]=1
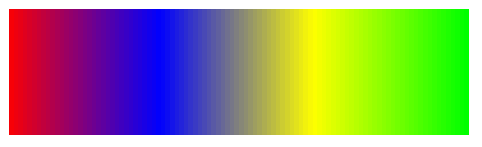
色が同じ色空間を使って指定された場合,その空間は補間に用いられる:
In[1]:=1
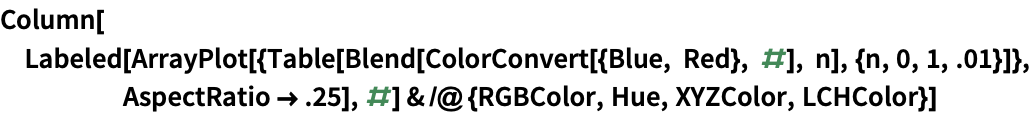
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-ifv4v9
Out[1]=1
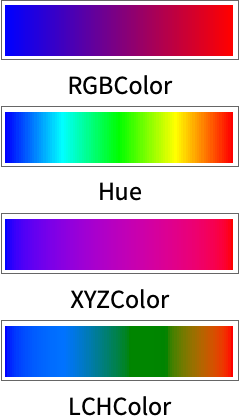
色が異なる色空間で指定された場合,補間はRGB空間で行われる:
In[2]:=2
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-2f70nl
Out[2]=2
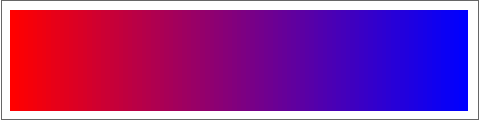
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gxnfx6
Out[1]=1
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dd70t7
Out[1]=1
ColorDataは"Gradients"と呼ばれる多くの予め定義されたBlendされた(混合)色を含んでいる:
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-cjry8n
In[2]:=2
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-c3ntr4
Out[2]=2
In[3]:=3
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-cycrq6
Out[3]=3
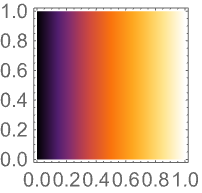
In[4]:=4
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-gq2qfa
Out[4]=4
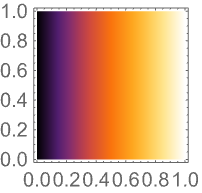
PolygonはVertexColorsを同じ重みで合成することをサポートする:
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-lzzww8
Out[1]=1
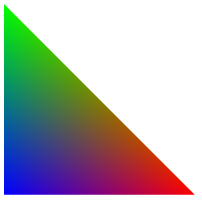
In[2]:=2
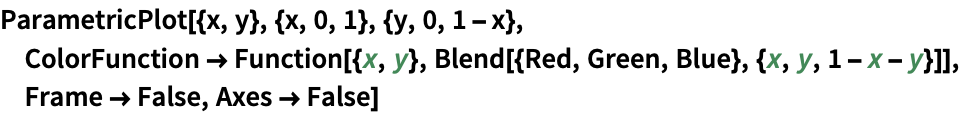
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-bib0m2
Out[2]=2
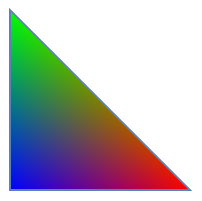
考えられる問題 (2)よく起る問題と予期しない動作
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-hr06n3
Out[1]=1
プロット関数では,ColorFunctionScalingを使って変数の大域的スケーリングを制御する:
In[2]:=2
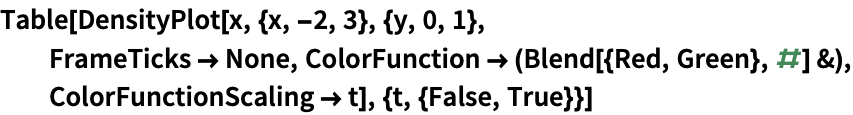
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-e1t1ms
Out[2]=2
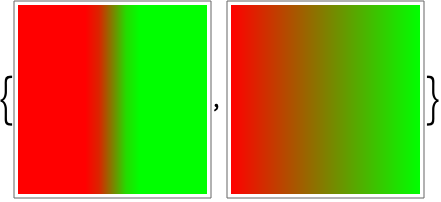
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dsrpbo
Out[1]=1
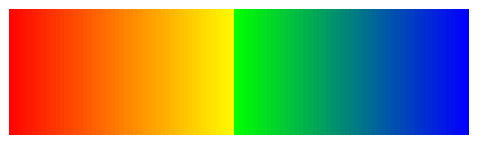
インタラクティブな例題 (4)インタラクティブな出力を含む例題
In[1]:=1
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-j9ec45
Out[1]=1
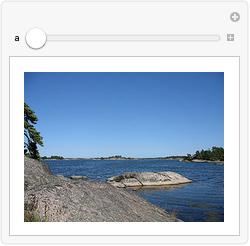
In[1]:=1
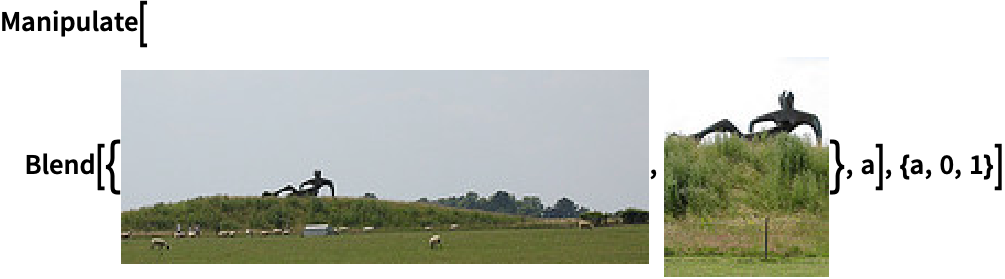
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-0uvh5c
Out[1]=1
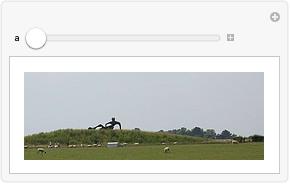
In[1]:=1

✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-odjkth
Out[1]=1
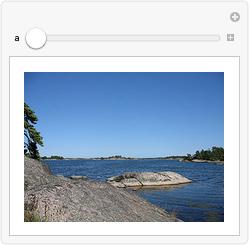
In[1]:=1
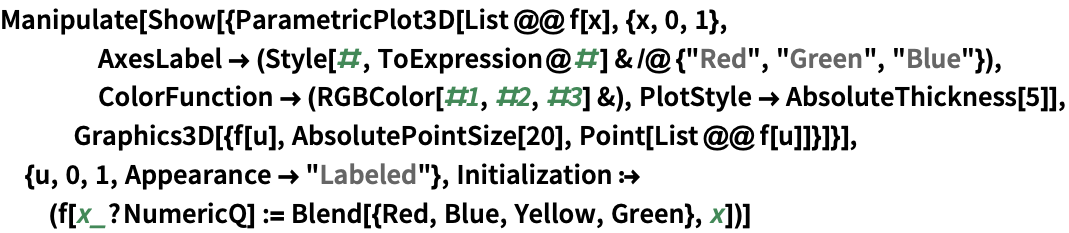
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-nypfdl
Out[1]=1
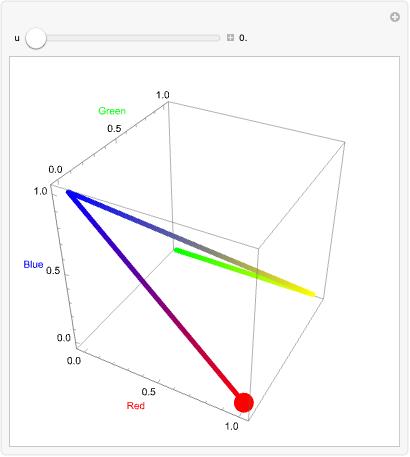
おもしろい例題 (2)驚くような使用例や興味深い使用例
Blendをプロットとともに使って合成した質感を生成する:
In[1]:=1
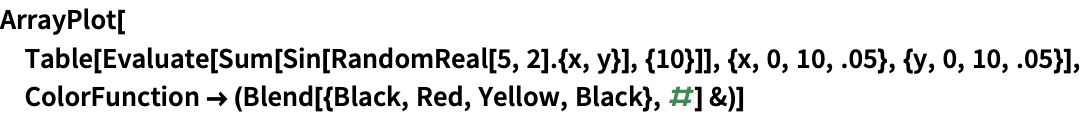
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-bgv0u2
Out[1]=1
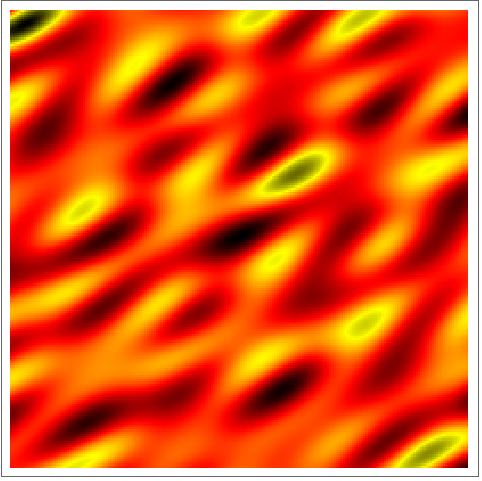
In[2]:=2
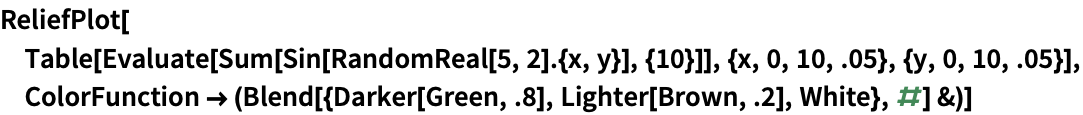
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-dg3m4k
Out[2]=2
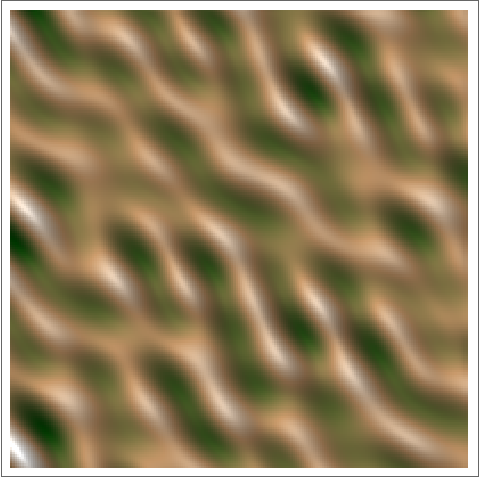
In[1]:=1
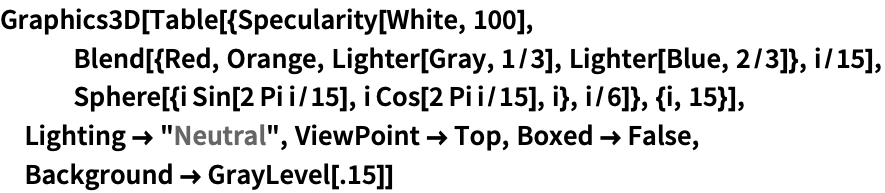
✖
https://wolfram.com/xid/0ldlcdd-13s1g
Out[1]=1
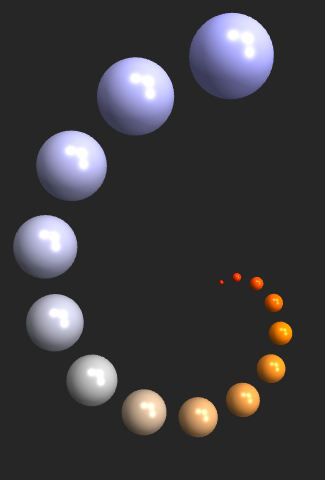
Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).
✖
Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).テキスト
Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).
✖
Wolfram Research (2007), Blend, Wolfram言語関数, https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html (2014年に更新).CMS
Wolfram Language. 2007. "Blend." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. Last Modified 2014. https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html.
✖
Wolfram Language. 2007. "Blend." Wolfram Language & System Documentation Center. Wolfram Research. Last Modified 2014. https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html.APA
Wolfram Language. (2007). Blend. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html
✖
Wolfram Language. (2007). Blend. Wolfram Language & System Documentation Center. Retrieved from https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.htmlBibTeX
✖
@misc{reference.wolfram_2025_blend, author="Wolfram Research", title="{Blend}", year="2014", howpublished="\url{https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html}", note=[Accessed: 30-March-2025
]}BibLaTeX
✖
@online{reference.wolfram_2025_blend, organization={Wolfram Research}, title={Blend}, year={2014}, url={https://reference.wolfram.com/language/ref/Blend.html}, note=[Accessed: 30-March-2025
]}